オリジナルボイスドラマ『収差~時の流れ~』完成
2019年10月15日。
ひとつの物語が産声を上げた。
『収差~時の流れ~』
この作品は誰一人欠けても成立しない物語だ。
出来上がるまでにはいくつかの偶然が重なった。
まず、メガネにまつわるドラマがなかったこと。
どうしてもこれまでのメガネにまつわるステレオタイプを取り払いたかった。
・メガネは安く買えるもの
・メガネを外すとなぜかキャラが美形になる
・メガネをしているのはインテリ
そして何よりキャストのおふたりに恩返しがしたかったということ。
すべてのはじまりは『ポリポーシスたちの憂鬱』のモノローグ収録を間近に控えた去年の12月末。
いつもお世話になっている難波さんの出演された舞台『今度は愛妻家』を観ていたとき、素敵なお芝居をされる彼女にお仕事を依頼することで恩返しすることができないか?と思い立った。
彼女の演技やセリフ回しはもちろんのこと、声が良いと思っていたのだ。
役によって声がまるでカメレオンのように変わる。
もちろん、アクセントも抑揚も。
のちに観劇することになる7月の舞台『マインドファクトリー』で難波さんはウグイス嬢として開演前アナウンスを吹き込んでいた。この人の声はすごい。いろんな人に聴かせたいという気持ちがさらに強まった。
企画当初はモノローグのようなものを吹き込んでほしいと思っていた。
しかし先のモノローグ収録日になり、出演者の吉田真理さんと川上ゴウキさんから『ボイスドラマのようなセリフのかけあいも面白そう』という言葉を聞いたときに考えが変わった。
ボイスドラマをやってみよう、と。
その類のものはTOKYOFMのラジオドラマ『あ、安部礼司』くらいしか聴いたことがなかったが、思えばこの作品に強い影響を受けていた。
とくに印象的なのはseason1で、主人公・安部礼司(小林タカ鹿さん)と恋人の岩月加奈(小関里恵さん)の初々しいやりとりが大好きで、実に微笑ましくて、大学時代の日曜の黄昏時によく聴いていた。
描写で魅せるテレビドラマとは違い、ボイスドラマは音と声で魅せていくもの。
聴いていた安部礼司的な雰囲気で、風刺の効いたメッセージを交えたマジメな物語にしようと構想が固まっていった。
ボイスドラマ。つまり声のドラマ。
ふと、声を生かせる共演者は誰がいいかと考えた。
とある人物の顔が浮かんだ。
もうひとりのキャスト、須田さんだ。
何を隠そう、私の父である。
父がアテレコの世界を去ってから約40年。
もう一度、現役のときの姿に戻ってほしいという思いがずーっとあった。
私が生まれたときは吹替とは無縁の仕事をしていた父。
しかしその昔は吹替の声優として活躍していたことから、いつか親孝行がしたいと思っていたのだ。
このタイミングだ、そう直感した。

マイクの前に立つ父の姿を調整室から観て、ジーンとこみ上げるものがあった。
当時と機材もスタジオの内装も違うが、まるでタイムマシンで40年以上も前に戻ったような気がした。
こうしてキャストは決まった。
ふたりの年齢的に、親子だ。
それならメガネにまつわる親子の物語はどうか?
よし、これで行こう。
作品を書き上げるにあたり、シナリオハンティングを決行した。
その場所とは福井県。

正確にはその隣にある鯖江市。
漫画でメガネを取り扱った作品はあるものの、お店やブランドの紹介そして各話ゲストの顔にどのフレームが似合うかというテイストなのでそれと絶対被らないように作風を吟味していった。
福井へ向かう前は都内のメガネ屋を舞台にしようと考えていた。
実際に店内に客として向かい、様子を見ながらどんな仕事風景なのかをチェックした。
ところが新人店員の成長物語ではありきたりだし、キャラは大人数出せないし、店員と客とのやりとりではドラマというよりもメガネ専門誌のコラムにある豆知識講座になってしまうのでドラマがないと判断し却下。
すでに出演者のおふたりには収録する時期を伝えており、タイムリミットが刻一刻と迫っていた。
はてどうしようかと思っていたところ、心の声からあるアイデアが。
『いっそ本場へ行ってみればいいじゃないか!』
思い立ったが吉日、すぐさま福井県へ。
北陸新幹線が開通したことで現地を身近に感じながら、実は東京から数えると実に6つも都県境を越えていた大旅行。
車窓より日本海側の風景を見ながら、いったい本場の職人たちはどのようにメガネと向き合っているのだろうか?
そう思ったとき、少しずつ本作の方向性が決まっていった。
鯖江に到着してまず向かったのは、めがねミュージアム。

実際にストラップを作る過程で、削ったり磨いたりして僭越ながら職人の気持ちになってみた。
工房の担当者が行う加工作業が見事で感動した。
対照的に私は四苦八苦の連続。
このときにバフ掛けのエピソードを思いついた。
さらに地域性を取り入れたいと思い、福井弁のことを本編に入れることにした。
めがねショップの方々から福井弁のレパートリーを教えてもらったのち、「現地の人は無意識で喋っているのでそれを聞くと良いですよ」とアドバイスをもらった。
そして市内のスーパーマーケットや駅に立ち寄って、対応してくださった相手とのやり取りの中でイントネーションを勉強していった。
が、その独特のイントネーションが実に難しい。
ゆえに瞳と鏡輔は都内から引っ越してきた一家という設定になった。
さらにメガネ会社や工房にもお邪魔させて頂き、そこで思わぬ事実を知った。
職人さんが減少しているという現実。
こだわりの技術が衰えゆく悲しき事態。
一度データを覚え込ませれば、いくらでも同じものが作れてしまう時代。
その工房の職人さんは、かつて職人だった人から年季の入った機械を譲り受けてメガネをすべて1から手作りされているという。
ところがこだわってオリジナルを生み出すよりも、近年はすでにあるものを利用して量産していく時代になっているようだ。
これって、まるで今日のドラマや映画にも同じことが言えるのではないか。
ふと、そう思った。
最後の決め手となったのはメガネ会社の担当者さんがおっしゃったこのセリフ。
「作る側の人間と売る側の人間はちがうんです」
これだ!
作る側=職人の鏡輔
売る側=販売員の瞳
とその時、すべての流れが完成した。
なお、現地の音声も使うことを決めていたので冒頭とラストの駅のアナウンスはその場で録った。
ちなみに歩行音も録ったのだがあまりに音が小さかったので、エンジニアの沼田さんに新たに素材を用意して頂いた(笑)
小ネタも満載で、本編には目やメガネにまつわるセリフやエピソードが出て来る。
さらに出演者のおふたりに関係のあるフレーズや小道具もたくさん登場する。
大阪のなんば、サンダーバード、平塚雷鳥などおふたりのことを知っている人にはツボに入る仕掛けとなっている。
 撮影:沼田裕太さん(プラチナムガレージ)
撮影:沼田裕太さん(プラチナムガレージ)
そして臨んだ収録当日。
難波さんは台本を細部まで深く読み込んで、前後の流れやセリフのニュアンスを何度も私に確認してくださった。
彼女のアドバイスのおかげで物語の流れが違和感なくスムーズになった。
こういうストイックな姿勢がみんなから愛される理由なんだなぁと思ったりする。
初めてお会いした朗読劇の時からその人柄がうらやましいと感じているのはここだけの話。
さらに福井弁を勉強してくれていたことを知り、とっても感動した。
父も久しぶりの収録とあって、役作りのためにあえて少し声を枯らしてくださった。
たとえ一日だけでもあの頃に戻れたことをとても嬉しく語ってくれた。
今回出演してくださった役者さんおふたりと担当してくださったエンジニアさん、吉田さんと川上さんそして取材に協力してくださった福井県鯖江市の皆さまへ惜しみない愛と感謝を贈る。
この作品はその誰一人欠けても成立しない物語だ。
次回作以降も現代性のあるテーマをもとに出演者にちなんだ小ネタをたくさん盛り込んで、いっしょにおもしろい作品を作り上げていく。


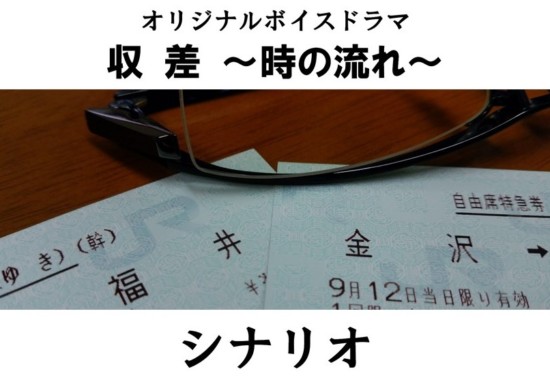
この記事へのコメントはありません。